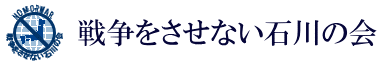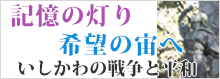戦争をさせない石川の会は「戦争シリーズ」講演会を12月2日、石川県教育会館2階集会室で開催しました。演題は「言論は死なずー戦後民主主義とメディアの再生のために」、講師は月刊『世界』前編集長の熊谷伸一郎さんです。
【講演要旨】
言論は死なず―戦後民主主義とメディアの再生のために
月刊『世界』前編集長 熊谷伸一郎
はじめに
日本における戦後民主主義の考え方には平和の問題、戦争に対する反省の問題、アジアに対する向き合い方など様々な問題が含まれています。この戦後民主主義をより深め、実践の中で研ぎ澄ましていくことが私の一貫した問題意識です。今日はそのことをメディアの再生と絡めてお話できればと思います。
右肩下がりの出版界-どのような現状にあるか
出版界は絵に描いたように右肩下がりが続いている。紙媒体だけ見ると1996年=2兆6500億円から2022年=1兆1292億円と半分以下になり、2023年は1兆円、2024年は1兆円割れも予想されている。特に「雑誌」の凋落ぶりが著しい。1996年=1兆5633億円から2022年=4795億に激減している。これは市民一人あたりの「雑誌」の購入冊数が低下している(1996年=13.6冊から2022年2.4冊)ためで、出版界の危機の大部分は「雑誌の危機」である。雑誌には賞味期限があり、本来は1か月、長くて2か月が限度。従って返品率が高い。2023年上半期の週刊誌の返品率は46%だった。
一方、電子出版は(紙の)雑誌を販売・市場占有率で上回るようになった。電子出版のほゞ9割が漫画である。出版界は漫画の有無で2分している。印刷や在庫のコストがかからない漫画を持っている小学館、講談社、角川書店は、ボロ儲けしていが、漫画を持たない出版社は大変厳しい局面を迎えている。
町の書店が一時期より1万店も減った一番の原因は、雑誌が売れなくなったからだ。定期雑誌の発行部数の減少により、書店がどんどん少なくなり、(書店に置かない)定期購読システムを持たない出版社は苦境が続いている。幸い月刊『世界』は2016年から定期購読システムを導入しており、現在は順調に発行部数も伸びている。
新聞の発行部数は、2000年から2022年までの23年間で5371万部から3085万部まで減少。世帯あたりの購読率も1.13部から0.53部に半減し、ほゞ2軒に1軒しか定期購読していない。新聞の発行部数の右肩下がりが顕著で2023年には3000部を割り、2024年には2500万部台が予測される。朝日新聞では2012年の762万部が最近では322万部に半減している。10年間で半分に減少した。朝日新聞のこの10年間の推移は、メディアがどのように衰退していくのかの象徴である。
なぜ既存メディアの苦境が続くのか
メディアの苦境が続くのは、①デジタル化による「無料」の情報空間の拡大、②スマホの普及による可処分時間の減少、③実質賃金の低下による図書購入費の減少、④消費者物価の高騰による図書の価格の高騰、そして⑤人口減少時代に突入したからである。
衰退するメディアの現場で起きてきたこと
2012年の安部政権誕生以降、「マーケティング」でヘイト本が興隆した。
・2014年、朝日新聞の吉田調書報道(慰安婦報道をめぐる撤回と謝罪)
・2016年 右派論壇誌・月刊『Haneda』創刊(花田紀凱編集長)
・2017年 飛鳥新社『今こそ、韓国に謝ろう』(百田尚機)
・2017年 講談社『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』(ケント・ギルバート)
・2017年 講談社『中華思想を妄信する中国人と韓国人の悲劇』(ケント・ギルバード)
・2018年 新潮社『新潮45』事件=国会議員・杉田水脈氏の「LGPTの人々には〝生産性〟がない論考を掲載、社内外の批判が高まり、同誌は休刊に。
・2019年 小学館『週刊ポスト』が「韓国なんて要らない」特集
言論メディアの「死のサイクル」・・・・図表2
言論メディアが売上至上主義を採ると、企画内容の劣化⇒読者の信頼低下⇒売上の低下⇒コスト削減となり、さらに売上至上主義に陥ると云われる「死のサイクル」が続く。
メディアの衰亡のあと、何が起きるのか
日本では政治的な弾圧を受けていないのに「萎縮と忖度」が横行している。ここが最大の問題である。政治家が個別の番組に介入した場合、拒絶しなければならないのは勿論だが、良質な言論・ジャーナリズムが消えていくのは〝弾圧〟ではなく〝商売上の理由〟である。言論メディアの「死のサイクル」にある「貧すれば鈍する」編集の現場がある。このためメディアを通じて世の中を知る私たちは、(真実を)知ることができない。権力に都合のよい情報しか知らされないことになる。
戦後民主主義の重要な点は、政府にあのような惨禍を起こさせないこと、つまり戦争を起こさせないために様々な仕組みを頑張って作ってきたこと。とりわけメディアによる権力のチェックである。この基本的なベースが失われているのではないか。
それでも良質な情報と議論は必要だ
私たちはメディアなしにはほとんど何も知ることができない。良質な情報と提供するメディアは民主主義社会には不可欠である。インターネットがあるが、情報と議論の流通過程に編集・編集者が存在する意義はあると思う。インターネット社会だからこそ、世の中には情報は無限にある。その中で読者のアンテナとなって今何が起きているのかを察知して、その情報を流通過程に乗せていくのが「編集」の役割である。
なぜメディアは〝消える〟のか。メディアには民主的社会に不可欠なインフラでありつつ私経営で営まれる両面性があり、民間企業だからだ。商業ベースだから消えていく。
ジャーナリスト・編集者になるということは、自分の良心に従って読者に最良の情報を提供することである。これに尽きる。みんなの利益、公共の利益を考えて情報を提供していくのが大原則である。
どう打開していくのか
3つの道筋がある。一つはNPOメディア=商業ベースで志しを廃れさすのではなく、視聴者や読者からの寄付を中心に営利を目的にしないメディア。二つ目は地域メディアの再構築=地方新聞、地域ラジオ等。三つ目は小規模な〝原則的〟メディアの多発・散発的起業である。この三つが重なりあって存在している。メディアは自分たちで作っていくという感覚を地域で取り戻そう。ジャーナリズムの精神、自分の良心に忠実なメディアを複数起業していくことが肝要である。
どのようなメディアを再構築するか
〝原則的〟なメディアとは、①市民の「知る権利」に奉仕すること、②権力を持つ人々の動きを監視・チェックすること、③市民社会で起きていること、議論されていることの共有、④言行が一致しているメディアであること、⑤タブーのない言論機関であること、⑥自らが良心に照らして裁量と確信できる情報・議論を伝達する、⑦専門性を磨く自己革新の努力をサポートするメディア組織である。
おわりに―新たな拠点をつくるために
お陰様で月刊「世界」は発行部数も増えており、再生産可能な体制になっている。私は今年7月に岩波書店を退職し、現在新しい出版社、再生産可能な会社を準備している。何のために会社をつくるのか。基本的には「世界」が持っている不変のポリシー、より良い社会を作っていく市民のための最良の言論を共有するための器を作るためである。これをキチンと維持していけば潰れることはないと思う。これが失われるとメディアの死、言論機関の死となる。私は今後、Webメディアや単行本の出版社を起業していきます。
(まとめ 非核・いしかわ編集部)
◎戦争をさせない石川の会が12月2日、石川県教育会館2階集会室で開いた「戦争シリーズ」講演会の講演要旨です。